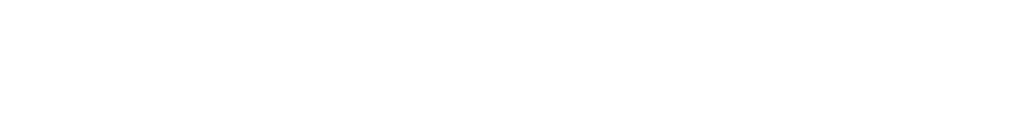証券口座ってなに?なんかめんどくさそうな感じがしますよね。でも実はあなたが銀行にお金を預けるときに銀行口座をつくるのと同じなんです。銀行にお金を預けるように、株は証券口座に預けるんです。
このページでは、株取引には必須の「証券口座の種類・違い」を解説します。どの証券口座を開けばいいかもわかるのでぜひチェックしてくださいね。
- 確定申告が面倒なひとは「特定口座 源泉徴収あり」
- 非課税メリットがあるのでNISAはかならず開設
証券口座(特定口座、一般口座、NISA)の違い
では早速ですが各証券の口座の違いを解説します。
| 口座の種類 | 確定申告 | 年間取引報告書の作成 |
|---|---|---|
| 特定口座 源泉徴収あり | 不要 | 不要 (証券会社がしてくれる) |
| 特定口座 源泉徴収なし | 必要 | 不要 (証券会社がしてくれる) |
| 一般口座 | 必要 | 必要 |
| NISA口座 | 不要 | 不要 |
それぞれの証券口座を順に解説していきますね。
①特定口座(源泉徴収あり・なし)
特定口座はどちらも1年間の取引を証券会社が自動でまとめてくれる点は同じですが、税金の処理が違います。
特定口座(源泉徴収あり)の場合は、税金の支払いまで証券会社がやってくれますが、源泉徴収なしの場合は、税金の支払いはあなた自身で行う必要があるわけです。
| 口座の種類 | 確定申告 |
|---|---|
| 特定口座源泉徴収あり | 不要 |
| 特定口座源泉徴収なし | 必要 |
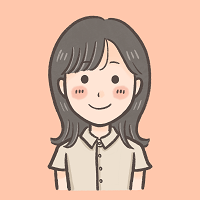 アップルちゃん
アップルちゃん確定申告の手間をかけたくない人は、特定口座(源泉徴収あり)を選べばOKです。
扶養に入ってるひと(学生や主婦)も特定口座(源泉徴収あり)を選べば、いくら利益が出ても扶養から外れることがないので安心です。
②一般口座
一般口座は全取引の損益を自分で計算して、税金の支払いをする必要があります。
2003年以前の特定口座制度がなかった時代には、こちらの一般口座で自力で「年間取引報告書」を作成する必要があったようです。ですが現状の制度ではメリットがないので、一般口座を選ぶケースはありません。



今は特定口座のおかげで凄く計算が楽になったので、一般口座を使うことはほぼありませんね。安心安心♪♪
③NISA
NISAは、NISA口座内での取引で得た利益に税金がかからない制度。非課税メリットはかなり大きいので、基本的に開設しましょう。



「特定口座+NISA口座」のようにあわせての開設もできます。
「NISAは長期投資用、特定口座は中期・短期用」のような使い分けもできますね。
まとめ 特定口座(源泉徴収あり)&NISAを開設すればOK
下の表にここまでの4つの証券口座をまとめました。
| 口座の種類 | 確定申告 | 年間取引報告書の作成 |
|---|---|---|
| 特定口座 源泉徴収あり | 不要 | 不要 (証券会社がしてくれる) |
| 特定口座 源泉徴収なし | 必要 | 不要 (証券会社がしてくれる) |
| 一般口座 | 必要 | 必要 |
| NISA口座 | 不要 | 不要 |
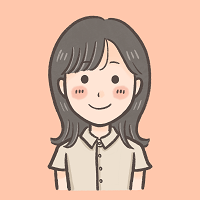
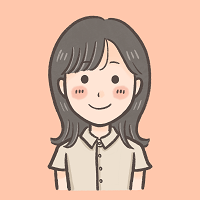
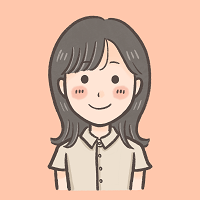
ほぼすべてのひとは、特定口座(源泉徴収あり)とNISAを開設すればOKです。
これでめんどうな税金処理からは解放されます。