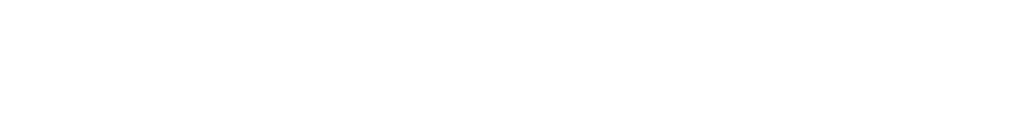知りたい人
知りたい人「ADRのメリットとデメリットが知りたい!」
「現地株とARDのどちらを買えば良いの?」
このような悩みを解決します。
ADR(米国預託証券)とは、米国市場で売買できる「米国以外の国の企業の証券」のこと。



欧米株や新興国株を米国株のように取引できるのがメリットだね。
ただデメリットも実はあるんだよ。
そこで今回の記事では、ADR(米国預託証券)のメリット、デメリットを解説します。
記事を読むことで、ADRのデメリットを理解でき、あなたが現地株とADRのどちらを買うべきかがわかりますよ。
- ADR(米国預託証券)のメリット・デメリット
- ADRと現地株のどちらを買うべきか
ADR(米国預託証券)のメリット・デメリット


ADRのメリットとデメリットを順番に解説していきます。
メリット1:外国企業(米国以外)投資できる
ADR(米国預託証券)の最大のメリットは、欧米株や新興国株など取り扱う証券会社が少ない株式を、米国株と同じ感覚で売買できること。
例えば、シェル(SHEL)やグラクソスミスクライン(GSK)などのイギリス株を米国株のように取引できるわけです。
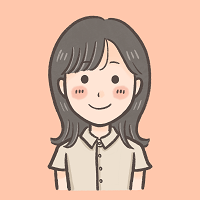
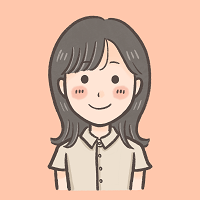
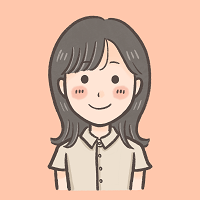
欧米株や新興国株を米国株のように取引できるのがメリットだね。
ただデメリットも実はあるんだよ。
デメリット1:上場廃止リスク
ただADRにはリスクがあります。
ひとつ目は「上場廃止リスク」です。
現地企業の株式は上場していても、ADRだけが上場廃止になることがあるのです。
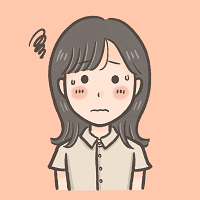
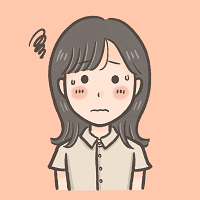
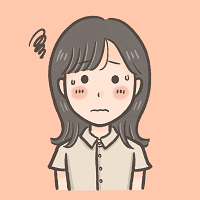
もし上場廃止に気づかなかった場合、証券会社やケースによっては価値がなくなる可能性も・・。
マネックス証券では以下のように記載されています。
当社でのADRの取扱いについて
マネックス証券>米国預託証券(ADR)
原株式への転換はできません。
当社においては、預託証券から原株式への転換手続きは取扱いません。
ADR廃止はそこまで珍しいものではない。
筆者の知ってる範囲でいえば以下の日本・欧米の企業がADRを上場廃止にしました。
- NTTドコモ(日本)
- 京セラ(日本)
- BTグループ(英国)
直近ではサノフィ(仏)のADRが楽天で買い付けが停止し、売り注文だけに取引制限が掛かりました。
また中国株のADRは、現地当局によって上場廃止にされる懸念も浮上してます。



ADRを利用する際は、この上場廃止や取引制限を十分に調べたうえで購入する必要があるんだ!
デメリット2:管理費用がかかる
もうひとつのデメリットは「管理費用がかかる」こと。
ADRを保有してるだけで、保有額に応じた手数料が発生することがあるのです。
マネックス証券には以下のように記載されてます。
一般的に四半期~1年毎に1株あたり0.25~5セント程度の管理費用がかかります。
マネックス証券>米国株取引で売買手数料以外の費用はありますか?
1株あたりで見れば「0.25~5セント」とそこまで大きな金額ではありませんが、株数が増え、長期で保有する株だとジワジワ効いてくるはずです。



手数料の支払いは、米ドルの預かり金から引かれる仕様なので、ADRを利用する場合は覚えときましょう!
【Q&A】よくある質問


ADRについてよくある質問についても触れときましょう。
質問1:配当は貰えますか?
ADRの現地株同様、配当を受け取る権利も得られます。
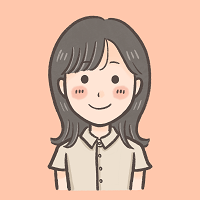
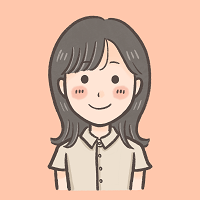
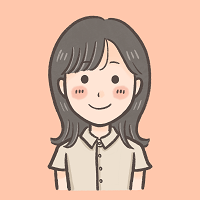
なので配当金を得たい投資家にとっても選択肢のひとつと言えます。
質問2:ADRの現地株の株価は連動する?
もし連動していれば現地株の値動きからADRの動きを予測、またその逆も可能になるからですね。
筆者も「連動してるか!?」と思ったこともありました。
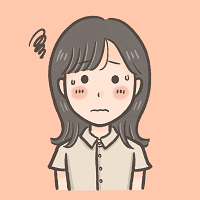
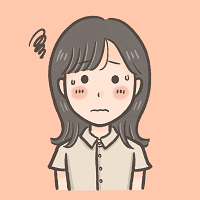
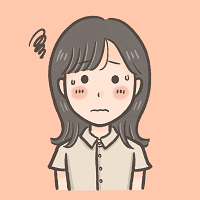
しかし実際のところ連動はしません。
需給バランス、為替、出来高などの他要因が関係するからです。
現地株とADRのどちらで買うべきか
ここまででADRのメリットとデメリット、よくある質問をまとめました。
ここで「現地株が買える株とADRなら、どちらを購入するのが良い?」と疑問に思うはずです。



楽天証券でADRの取り扱いがあるけど、サクソバンク証券で現地株の取り扱いがあるケースなどだね!
結論からいうと現地株があるなら、現地株で購入するのをおすすめします。
ADRの場合、管理手数料がかかったり、上場廃止リスクがあるからです。
あくまでもADRは現地株が買えない場合の選択肢との位置づけにしておくのがベストでしょう。
ということで今回の記事はここまでです。
最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。